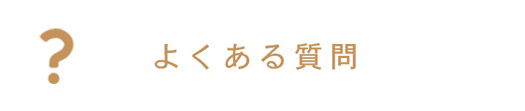【第2回 吹田の歴史】いけず石──石に込められた真の意思とは
- 川ノ何某
- 2025年8月23日
「吹田の歴史」シリーズ、今回お届けするお話は「いけず石」です。
……ナニソレ?
石との遭遇

「大きくて重そうな石が道路の端に堂々置かれている」という場面に遭遇したことはありますか?
1個の時もあれば、何個も並んでいる時もあり、大抵は建物の隅に置かれています。まるで「何かから守っている」かのように、です。
そうです。それこそが「いけず石」です。
「いけず」は「意地の悪い」や「強情」等の意味を持つ関西弁で、いけず石は「意地の悪い石」「強情な石」となります。これだけ聞くとあまり良いイメージは持てませんね。
一体この石の目的は何なのでしょうか。地元の古老に聞いてみました。
筆者「いけず石は何のためにあるのですか?」
古老「車避けだね。車が普及してから路上駐車とか、塀や軒先にぶつけられて壊される事故とかが増えてね。その対策で皆置いたんだよ」
いけず?な歴史

【地元の古老より提供:写真左に見える橋は高浜橋】
日本で自動車が本格的に普及し始めたのは高度経済成長期の後半、吹田万博も開催された昭和40年代(1965年〜1974年)になります。
生活水準の向上や高速道路の開通などにより、一般家庭でマイカーブームが始まり、急速に自動車の数が増えました。

【地元の古老より提供:車は昭和43年(1968年)販売開始の高級車「トヨペット コロナ マークII(初代)」】
しかしその一方、自動車事故が増加し、その中でも住宅地における路上駐車や家との接触事故は住民にとって悩みの種でした。
そして、誰が言い始めたのか「車にとって邪魔なものを家の近くに置いて家を守ろう」という考えが現れ、登場したのが「いけず石」でした。

【京都府京都市上京区智恵光院通寺之内下ルのいけず石。曲がり角に設置】
いけず石の本家は京都府京都市と言われ、およそ1000年前の平安時代、牛車や荷車などが境界を跨いで私有地に入らないようにする目的で置かれたのが始まりとされます。
いつからいけず石と呼ばれるようになったのかは定かでありませんが、時代が変わっても人々は車両を起因とする問題の解決に石を求めたのでした。
いけず石の分布
ウェブサイト『いけず石調査』によると、圧倒的に多いのは関西です。もちろん吹田市も含まれ、私もいくつか見かけたことがあります。
しかし、「意識して探したことは今までなかった」ので、今回いわゆる旧吹田地域(吹田市の大元となる旧吹田町の前身「吹田村」の地域)でいけず石を求めて駆け回ってきました。その結果、さまざまないけず石と出会うことができました。
魅力的ないけず石ばかりですべて紹介したいところですが、膨大な量になりますので「個人的にこれは良い!」と思ったいけず石を5セットご紹介します。
【1】どっしりいけず石:田中町(内本町1丁目)

塀の角で存在感を示すいけず石です。サイズは大きく重厚感もあり、威圧感すらも感じます。この石1個を運ぶだけでもかなり大変だったのではないでしょうか。
【2】徹底抗戦ないけず石:都呂須町(内本町2丁目)

過去に何かがあったのでしょうか、「ここには絶対近づかせない」という強い石改め意志を感じる大量のいけず石です。均等な間隔で並んでいるので美術点も高いです。
【3】転職いけず石:神境町(南高浜町)

【4】カーブミラーを守るいけず石:下新田町(南吹田)

カーブミラー(だいだい色の支柱)の側に置かれたいけず石です。カーブミラーは曲がり角の安全を守り、いけず石はそのカーブミラーを守る、まさに二人三脚ですね。
【5】仲間外れないけず石:西奥町(内本町1丁目)

一見、形状と間隔が統一されているいけず石達ですが、実は1個だけ異なるいけず石がいます。探してみましょう。
いけず石も歴史の一部

取材中に知り合いの方から「あんた何してるの?」と声を掛けられて「いけず石を調査してます」と伝えたところ、「物好きやね〜」という返事がきました。
確かに路上の石をまじまじと観察して写真もパシャパシャ撮っていればそう思いますよね。
昔はもっといけず石があったそうですが、街並みの変化と共に数を減らしているとのことです。確かに、新しい街並みのところではほとんど見かけず、古い街並みのところでは多く見かけました。
ネガティブな名称とは裏腹に「家の守り石」という大役を担ういけず石、読者のみなさまがお住まいの地域にもいけず石はありますか?
参考ウェブサイト
- ニッポン旅マガジン『交差点の角にある! 京都名物「いけず石」とは!?』 https://tabi-mag.jp/ikezu-stone/amp/ (参照令和7年・2025年7月28日)
- いけず石調査 https://sites.google.com/view/ikezuishi-shirabe/ (参照令和7年・2025年7月28日)
スペシャルサンクス
- ご近所の古老
- 生まれも育ちも京都の先輩
- いけず石の皆様
<「ちょい足し」吹チャン!>
今回の記事とあわせて、「歴史」つながりのこちらの記事も読んでみてください。
【第1回 吹田の歴史】吹田に息づく古の地名「川面町」──その読み方と歴史をたどる
本日も読んでいただきありがとうございました!
◆◆「吹チャン!」公式Instagramのフォローもお願いいたします◆◆
https://www.instagram.com/suichan11/◆◆「吹チャン!」公式Twitterのフォローもお願いいたします◆◆
https://suichan.jp/otoku新しいお店の情報や市内のイベントなど、すでに誰かから投稿されてそうな情報でも歓迎します。
- 昨日のアクセス数:31909
- 今日のアクセス数:03412
- これまでの合計 :24227629